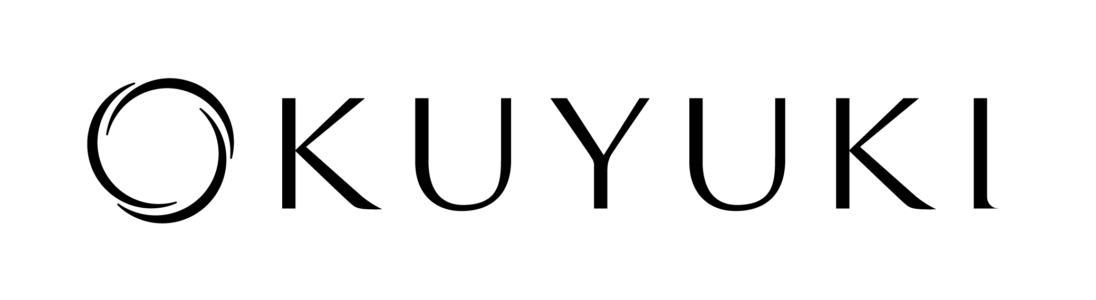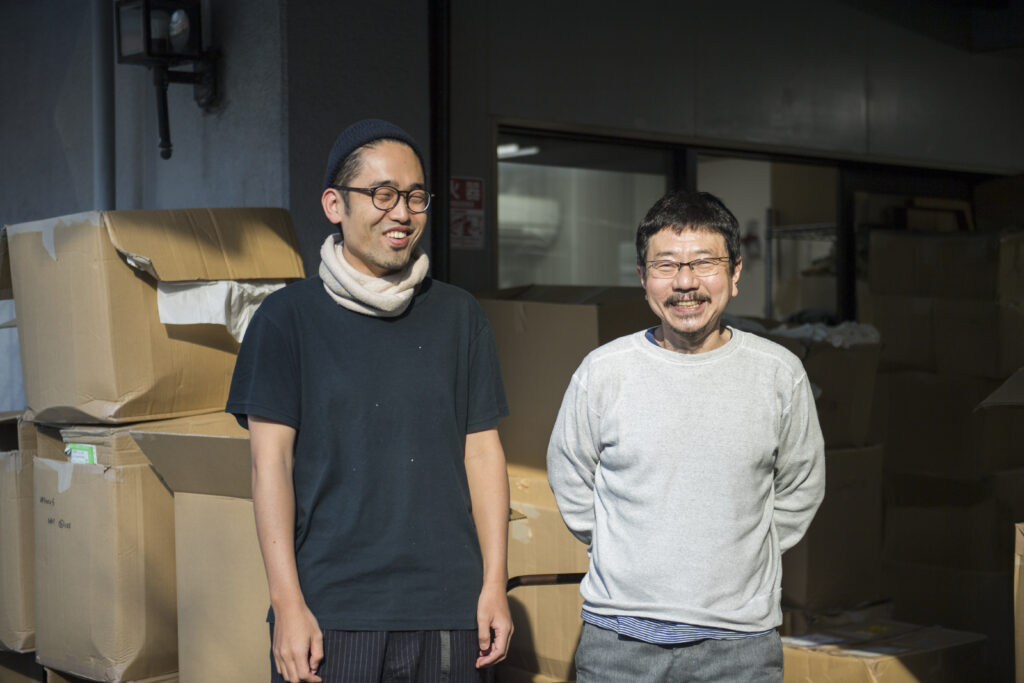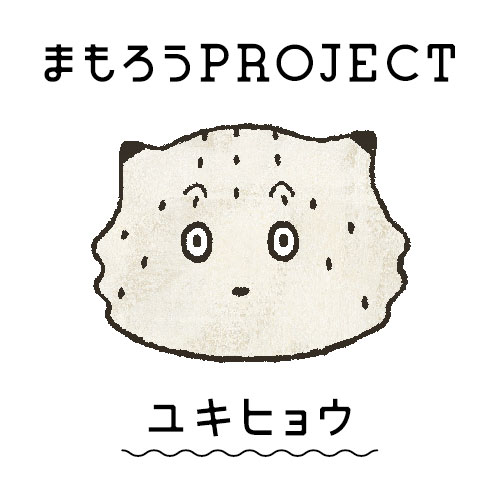企画展「はじまりの白」(2021.8.1~10.24) に出店してくださる皆様に、
なぜその分野で生きることを選んだのかを聞くシリーズ。
最終回は、カカオの生産からチョコレートの製造販売まで、南米コロンビアで一貫して手がける「CACAO HUNTERS」の創業者であり、カカオハンターⓇの小方真弓さん。
豆からチョコレートを作るのが「Bean to Bar」なら、CACAO HUNTERS のチョコレートはいわば「Tree to bar」。チョコレート会社の開発員だった小方さんが、地球の裏側に拠点を移してまで追い求めた“夢”、そしてその先に見つけた喜びとは。

カカオ・ブランコとの出会い。そして、コロンビアへ
大学で栄養学(管理栄養士)を学んだ後、卒業後は製菓原料チョコレートメーカーに入社して開発部門に勤めていた小方さん。今でこそチョコレートの原料がカカオであり、カカオ生産国や栽培現場にまで目を向けられることも増えてきたが、当時はまだまだその分野に詳しい人が数少ない時代だった。
「このチョコレートの原料は誰がどうやって育て、収穫して私たちの手元にきたのか」
カカオの世界を知らずにチョコレートを開発することに疑問を感じた小方さんは、会社をやめ、カカオの生産国や、ヨーロッパの消費国など、単身で世界へ飛び出すことを決意したという。カカオがチョコレートになるまでの長い道のりを、自らの目で見て、肌で感じること。それが、カカオハンターⓇとしての「旅」の始まりだった。
その後、チョコレートの技術コンサルタントとして活躍しながら、カカオの生産地だけでも15カ国を訪れた小方さんが、やがて拠点として選んだのは南米コロンビア。
その理由の一つとなるのが、「カカオ・ブランコ」と呼ばれる種が白いカカオとの出会いだ。(通常のカカオの種子の部分は紫色をしていることが多い)
「カカオ・ブランコはチョコレートやカカオに携わる人たちの一つの夢なんです。数が少ないので、出会った瞬間の喜びというのは別格です。カカオは花粉が混じりやすい植物なので、白いカカオでも、隣に種子の色が紫色のカカオを植えると、次第に混ざっていきます。なので、本当に真っ白なカカオはすごく少ないんです。数が少なく、さらにピュア。誰とも混じっていないというか。そんな感覚がありますね。」



カカオの実を割り、さらに種を割った写真
一度は見つけられず日本に帰国したというが、その後様々な地図から研究を重ね目星をつけて行くと、見事発見。トレジャーハンターさながらの冒険物語だ。
その後、コロンビアのカカオのポテンシャルに魅了された小方さんは、さらに深くコロンビアと関わっていくこととなる。
カカオと言えばガーナなどアフリカ大陸のイメージがあるかもしれないが、その起源は南アメリカ大陸のアマゾン川流域西部であるとされる。エクアドルではカカオの成分が付着した5300年前の土器が発見されているほど、長い歴史を持っているのである。
そして、コロンビアはエクアドルの北側に接している国。長い年月のなかで自然交配されたカカオや、海や山と言った様々な土壌と気候のもとで育まれるカカオなど、その多様性は他に類を見ないのだそうだ。

それに加え、コロンビアで繋がったチームメイトと、その土地に根付いていた文化が、小方さんをカカオの世界の深淵へと導いていった。
「コロンビアでできないことは、他でやってもできないだろうという考えがありました。コロンビアでは生産者がチョコレートを飲む文化があるのですが、その文化が今でも残っているのは、主にメキシコ、グアテマラ、コロンビア*1。だから生産者自身がカカオを育てることにすごく誇りを持っている人もいらっしゃる。自分たちが作ったチョコレートを家で飲む文化もあったというスタートラインが少し他の国とは違うということもありました。」
*1 一部のエクアドルやペルーなどでも飲用されている。
コロンビアの人々との縁と、カカオの多様性、そして、食文化。
小方さんがコロンビアに拠点を移すには十分すぎる条件が整っていたのである。
良いカカオは、良い循環から
ご存知の方も多いかもしれないが、カカオがチョコレートになるまでの過程をあらためて整理してみよう。
【カカオの栽培→実の収穫→実の中を取り出す→果肉と種の発酵→乾燥→熟成】(輸出)【ロースト→可食部(カカオニブ)を分離→カカオニブを摩砕してペースト(カカオマス)状に→砂糖などの副原料を加えて更に微細化→精錬→成形】
書き出してみると、非常に多くの製造工程を経てチョコレートが作られていることがよく分かる。そして、ここに仲買業者や輸出/輸入業者、チョコレートメーカーなどが関わることで、ようやくチョコレートという形で消費者に届くのである。
CACAO HUNTERSのチョコレート製造の特徴の一つとして、この複雑な流通経路を一本化し、生産から製造・販売までを一貫して手がけるダイレクトトレードというものがある。
一般に、カカオは投資の対象であり、先物取引によって価格が決まる。それはつまり、生産者はその価格設定に関与できないということだ。
一方で、CACAO HUNTERSのダイレクトトレードでは年間の取引価格そのものを生産者との間で決めているという。さらに、品質の良いカカオへの技術指導を行いながら品質向上を促し、その結果に対して買取り金額を上乗せするという独自の制度を導入。これにより、カカオ生産者への迅速な支払いと農業開発の促進を実現している。消費者にとってはトレーサビリティが担保されることにも繋がっており、CACAO HUNTERSで取り扱うチョコレートは、原料のカカオを生産した農家、さらには収穫した個人名まで追うことができるというから驚きだ。
「ダイレクトトレードのいいところは、状況に応じて、生産者と一緒にマーケットを作っていくことができて、かつ、消費市場にもマーケットを作れること。生産者にも消費者にもメリットがあり、楽しんでいただけることが、持続可能な生産に繋がります。」
生産者の持続的なカカオ生産、という観点からはフェアトレードとよく似ているように感じるが、フェアトレードは国際市場での価格変動に対して最低価格を保証することが最たる目的となっている。個々のカカオの「品質」に対して、それぞれ適正な価格で取引をする、というところにはまだ行きついていないのである。

コロンビアの先住民の末裔アルアコ族
チョコレートの世界では、生産国と消費国との間に“距離”がある。自分たちが作るカカオが、どのようなチョコレートになって、どのように消費者のもとへ届くか、生産者自身は知らないことが多い。小方さんは、カカオ生産者が、生産することに対する誇りを持てるような仕組みにこだわる。
「生産者としてのものづくりの皆さんがチョコレート市場に近くなることが大事です。品質の高いカカオに対して対価をお支払いする。それによって、みんなのモチベーションと誇りを上げていく。カカオからチョコレートを作る私たちは、そこからさらにクオリティとしての上の部分を目指していくという循環なんです。」
生産者の立場から見れば、良いカカオができれば、その働きに対してしっかりと還元されるのは、ごく当然のこと。そして、良いカカオからは、より美味しいチョコレートを作ることができる。そこで生まれる消費者の喜びが生産者に伝われば、新たなモチベーションとなっていく。マーケット側からの一方的なサポートではなく、循環の中で高めあっていくというのが小方さんの考えだ。
次の世代へ繋がるカカオ
今回話を聞いていく中で、カカオをまるで我が子のように語る小方さんが印象的だった。カカオはその時々の天候によって大きく味が変わるというが、その個性をいかに理解して生かせるかということが、チョコレートの出来に繋がる。味を安定させるには、異なる時期・天候で育ったカカオを上手くブレンドすることも重要だ。
「納得のいかないチョコレートになった時の私の落胆といったらもう。機嫌が悪くなるんです。自分のところのチョコレートに100点をつけたことはないですから。いって70点です。まだいけるよねこのチョコレートと思うので。」
そう熱く語る小方さんは、さながら芸能界の卵のマネージャーのよう。大切に育てたカカオだからこそ、最大限にそのポテンシャルを引き出してやりたいのだろう。
生産拠点であるコロンビアの工場では、これまでに作られたチョコレートが製造番号ごとに保管されているといい、小方さんは、それぞれがいつ、どんな天候で育ったカカオからできたものかを全て記憶しているという。
そんな並々ならぬ情熱をカカオに注ぐ小方さんが、カカオ生産を持続可能なものとしていくために最も大切にしているのは、何より出来上がった商品が美味しいか美味しくないかということ。
「そもそも私たちはものづくりの人間ですから、一番大事なのはそこにある商品なんですよね。エシカルとかサステナブルとかを全面に出したことはほとんどないです。純粋に味で皆さんに判断していただく。ただ、それだけの味が出てくるというのは、それだけの仕事をしているということ。一度来ていただいても、次がなければ循環には繋がらないですし、お客様が美味しかったよと言っていただくことが、また次の機会に繋がります。」
CACAO HUNTERSには『あなたの興味が、私たちの宝』というマニフェストがある。
生産者はカカオが辿り着く先へ、消費者はチョコレートのバックグラウンドへ、それぞれ好奇心を持ち続けることが、喜びや幸せを生み、循環を促し、そして次の世代へと繋がっていく。
幼い頃にチョコレートに出会い、チョコレートメーカーにまで勤めた小方さんだが、カカオという素材に密着しているからこそ、チョコレートを作るのは今が一番楽しいという。
「当時チョコレートメーカーに勤めていたときは仕事で、今は人生です。
だからチョコレートを作ることをあんまり仕事だと思っていないんです。これが自分のできることで、やるべきこと。私たちが経験してきたものをシェアしていくことが自分の人生そのものなので、生きている感じがします。」
チョコレートには負のイメージが付いてまわることも少なくない。過酷な労働現場、貧困、児童労働など、私たち消費者が知るべき課題も多くあるだろう。
どう向き合うかは人それぞれだが、美味しいものを美味しく食べるという、私たちの等身大の消費が生産者の喜びに繋がっているのだとすれば、それに勝ることはない。
そして、CACAO HUNTERSのチョコレート商品はまさにそんな存在だ。
東京駅改札内にあるグランスタに2020年にオープンしたCACAO HUNTERS Plusでは最高のチョコレートをさらにスイーツに生まれ変わらせた商品も多く取り扱っている。
社会的な課題に対する正義感もよいが、純粋に”良い”ものが、結果的に明るい未来に繋がっていてくれたら嬉しい、そう思ってしまうのは怠慢だろうか。小方さんの話を伺いながらそんなことを考えていた。

CACAO HUNTERS JAPAN
カカオハンター® 小方 真弓さん プロフィール
1997年に製菓原料チョコレートメーカーに入社、以来6年間商品開発や企画開発に従事。在勤中にカカオの世界を知らずにチョコレートを開発する自身に疑問を感じ、一念発起して単身でカカオ生産国を旅することを始める。
2003年にチョコレートの技術コンサルタントとして独立し、その報酬を全てカカオ生産国で学ぶことに費やす。NGOやアジア開発銀行のチョコレート復興プロジェクトに従事しながら、現在まで15カ国のカカオ生産国を旅する。
2009年にコロンビアを訪れた際にこの国のカカオのポテンシャルに魅了され、2010年Cacao de Colombia S.A.S. に自己資金を投資して経営参画、以来活動拠点をコロンビアに移し、研究開発ディレクターとして現地のカカオ発掘、カカオ豆品質向上、生産指導、生産農家の発展に勤めている。
2013年12月同社にてチョコレート工房設立、2016年9月新工場設立、コロンビア初のInternational Chocolate Awards 金賞、特別賞受賞チョコレートの開発・製造に携わる。カカオ・チョコレートの国際コンクール審査員の他、カカオの世界を多くの人に知ってもらうため、各国でセミナーやコンフェランスも行う。
(取材・文 三山星)